COLUMN 住宅コラム
今週のTOPIC「雨樋(あまどい)の重要性!!」
雨どいには、
雨から建物を守るために屋根に降り注いだ雨を集め、
地面に流す役割があります。
大雨が降っても水があふれないように、
屋根の面積や地域の降水量を参考にして、
といの大きさや取り付け場所を検討します。
◆雨どいとはなぜ必要か
雨どいとは、屋根面の雨水を集め、
地上に流すための設備です。
軒先に水平方向に設けられるものを軒どいといい、
その形は雨水を受けられるように
半筒状もしくは凹型をしています。
軒どいに対して垂直に円筒状または
角形の竪(たて)どいが接続され、
地上に雨水を流します。
もし軒先に雨どいがないと、
軒先のあちこちから雨だれが生じ、
雨だれの落ちる部分の植栽を傷めたり、
溝や水たまりができたりします。
またその雨だれが地面で跳ねて外壁や基礎に当たり
建物を汚したり傷めたりします。
軒どいから竪どいを経由して
地上まで落ちてきた雨水は、
敷地内の雨水枡にたまります。
そのまま敷地内の地中にしみこませるか、
道路にある雨水用の下水管に接続して流します。
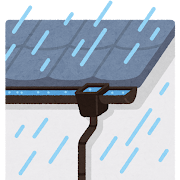
◆雨どいの種類
雨どいの材質は、
安価で施工性のよい樹脂製のものが主流です。
ステンレス、銅、アルミ、ガルバリウム鋼板
といった金属系の雨どいもありますが、
高価になります。
表面はプラスチック製ですが
芯にステンレスを用いて耐候性を高めたもの、
プラスチックの表面に特殊樹脂を巻いて
色褪せや変色に強くしたものなど、
様々な種類が出ています。
ひと昔前は板金屋さんがその家に合わせて雨どいを
作成・取り付けしていました。
しかし手間がかかるため、
今では多くの新築住宅では既製品を使用します。
各メーカーの出している雨どいの既製品には、
色、形、大きさともに様々なタイプがあります。
地域別降雨量や屋根面積にあった排水計画を立て、
といの径(大きさ)や数を決めます。
また、外観のアクセントになる部分でもあるので、
美観を損なわない外観イメージにあう
デザイン、色を選びましょう。
◆雨どいのメンテナンス方法
雨どいは、常に太陽や風雨にさらされているため、
劣化しやすい設備です。
樹脂製の場合10年程度で劣化が目立ち始めます。
雨どいはいくつかの部材をつなぎ合わせているため
つなぎ目が外れたり、部材そのものがたわんだり
することもあります。
また、葉っぱやゴミがたまりやすい場所なので、
手の届く範囲、目の届く範囲であれば、
定期的にゴミを取り除き、
水漏れや破損などがないか点検するようにしましょう。
しかし屋根の軒先など高い部分にあるものに関しては、
一般の人が行うのは危険です。
屋根の葺き替え時などに、併せて点検してもらい、
必要なら交換等を行いましょう。
退色や汚れが目立つようであれば、
ペンキを塗り替えると美しく蘇ります。

それでは、また!!
